犬や猫などの動物のお医者さんといえば、やはり獣医さんですね。自分のかわいいペットの病気を治してくれる神様のような存在です。
では、獣医さん、つまり獣医師になるにはどうすればよいのか見ていきましょう。
獣医とは
獣医とは、動物の疾病の治療や予防を職業としている動物の先生です。獣医師国家試験に合格して農林水産大臣が交付した獣医師免許を取得することで、動物の先生になることができます。
昨今の獣医について
時代とともに診る動物が変わってきています。
獣医の仕事は、元々は、産業動物の診察が主でした。
最近では、ペットを愛玩動物や伴侶動物として飼育(同居)する人が
増えてきたことで、街の獣医が身近になり、子供のころお世話になった
獣医にあこがれて「獣医さんになりたい」と思う人が増え、今では人気の職業ともなっています。
また、最近では、ハリネズミやフェレットなど、
珍しい動物を飼育する人が増えたことで、エキゾチックアニマルという、
珍しい動物専門の獣医も増えてきています。
小動物の種類も多岐にわたり、獣医の専門領域も広がってきています。
専門領域のペットまで治療できる獣医は、それこそ、飼い主さんから見るとまさに、神の手を持つ救世主です。
では、そんなペットと飼い主さんの救世主でもある獣医になるには
どうすればよいのでしょうか。
次の章から様々な角度から紹介していきます。
獣医になるには:仕事内容と適正
獣医になるにはどのような進路を選択するとよいのでしょうか。また、獣医の仕事内容や適性についても紹介します。

1.獣医になるには
獣医師なるには、国家資格が必要です。
そのためには、獣医系の大学に入学して6年間学ぶ必要があります。
ただし、獣医系の大学は国立・私立合わせても、日本には17校しかありません。
しかも、獣医大学は難易度が高く、一部では医学部のレベルを超えているとの説もあります。
また、獣医大学によっては、動物や魚の研究に力を入れている大学やペットや産業動物などを見る動物の先生になるために力を入れている大学もあります。
獣医を目指すために、大学を選択する際には、自分が研究職に就きたいのか、動物の先生になりたいのか十分考えて大学を選ぶとよいかもしれません。
6年間しっかりと勉学に励み獣医師国家試験に合格すると獣医師としての第一歩を踏み出すことになります。
2.獣医の仕事内容
獣医の仕事といえば、以前テレビで有名になった「口蹄疫」
など、一般人のペットではなく産業動物の伝染病の予防や診療
犬や猫のペットフードの安全性を確保する研究や動物園・水族館での勤務医製薬会社で医薬品開発や食肉との安全確保や食品衛生の管理等、活躍の場がたくさんあります。
最近では、エキゾチックアニマルといって、国内に生息していない希少動物をペットとして飼育している人も少なくありません。これらの動物のための専門の獣医もいます。
3.適正
獣医になるためには様々な専門的な勉強を6年間継続していかなければいけません。
そのための忍耐力や集中力が必要となってきます。
では、獣医に向いているのはどのような人でしょうか。
動物に関する幅広くまた、深い知識が必要になってきます。
また、その知識は日々進展していきますので、自ら勉強し研究を進めていけるようにいち早く情報をキャッチできることも必要です。
さらに、特定の動物が好きだらや、単に動物が好きだからでは、獣医の仕事は務まりません。
愛情があることは、もちろんですが、ペットの病気を見る立場として、感情移入をしすぎることは避けなければいけません。なぜならば、最善を尽くしても助からないといった辛い思いもあるからです。そのようなときに落ち込んでしまい、立ち直れるようにしなければ獣医の仕事は務まりません。そのため、冷静さも必要となってきます。
他にも急患対応や大型の動物を診療する際の体力も必要です。(人間の場合も、夜間急に体調が悪化することもありますよね…)
また、人とのコミュニケーションが上手にとれることも必要です。
動物病院にペットをつれてくる飼い主さんの気持ちや要望をくみ取ることも、診察においてはとても重要になります。
なかには、「動物は好きだけど人は苦手」という方もいますが、このようなタイプの方は、ペットや産業動物の先生向きではありません。
動物は「ここが痛い」や「気持ちが悪い」とは、話してくれないので、飼い主さんとのコミュニケーションや、動物の様子を見て、どこの調子が悪いのかを一瞬で見抜かなくてはいけません。
初めて診る子も「初めてだからわからない」といって断ることはできません。
また、ひっかかれたり、かまれたりは当たり前の世界です。それでも、患者さんである動物の健康を第一に考え、
飼い主さんの同意を得るために人間関係を大切にしながら、動物の病気の治療をします。また、避妊や去勢もします。
余談になりますが、ペットの避妊手術について、著者である私が飼育しているペットの先生は、猫の避妊と手術のみしか実施しません。
その理由が、犬は、犬種によって体格に差があるので麻酔の投与量や、手術が体に与える負担を考慮しながらの手術になるので、猫の避妊と去勢手術しか実施しないのだそうです。しかも、去勢は8か月以上もしくは体重が3Kg 以上の5歳以下と限定しています。避妊手術の場合も、生後6か月以上もしくは体重2Kg以上で、5歳以下と限定しています。
体重を限定している理由は、限定した体重以下だと、病気の可能性や、手術に耐えられない可能性があるからです。獣医によっては、この条件に満たなくても手術をしてくれる病院もありますが、やはり健康面での保証はできないとのことでした。
獣医の中には、地域猫のTNR(Trap“仕掛けて”Neuter“不妊手術をして”Return“元の場所に戻す”といった活動をしている先生もいます。TNR活動など、動物を取り巻く環境をよりよくしていく仕事も、獣医の役割の一つといえるかもしれません。
※TNR処理をした猫のことを「さくらネコ」といいます。
猫の耳先を「さくらの花びら形」にカットしているのでそう呼びます。
実は、私も昔の夢は獣医師でしたが、ただ好きなだけではなく、すべての責任を受け入れる、そこまでの覚悟ができてないと感じ、製薬株式会社の研究職の道を選択しました(獣医師免許は持っていません)。
一方で、研究職にも会い変な点はありました。研究職に携わる人たちもみんなが動物が好きなのですが、動物の命を扱うこともあるため、保護団体や世間の風当たりが強く、本当に動物が好きなのに、そのことを理解してもらえない、といった経験もありました。
(一例ですが、私の働いていた会社では、ペットの動物が行方不明になったという理由で「遅刻」が免除されるくらい、みんなが動物を大切にしていました)
獣医師によっても診察方法がそれぞれあります。
先進医療を取り入れたいか、飼い主さん目線で動物を診るか、利益に走らず価格を抑え、動物病院へ多様ハードルを下げるような先生になるのか、たくさんの獣医師の形があります。
17校しかない獣医系大学ですが、それぞれ大学によってとくと湯や得意な分野があります。これから獣医を目指そうとしているあなたが、どんな獣医になりたいのか具体的に想像してみると、どの獣医系大学に入ればよいのかが決まってくると思います。
また、私と同じように(笑)他人のコミュニケーションをとることが苦手な場合は、研究系の仕事をお勧めします。
研究系の仕事でしたら、チーム内の人とのコミュニケーションだけで済みますので、動物病院と比べるとコミュニケーションの範囲が限定された状態で黙々と研究を続けることができます。
そこで、自分の専門知識を増やし、研究成果を発表することで社会へ貢献していく働き方も可能です。
獣医になるには何年かかる
それでは、いろいろな活躍の場がある獣医になるためには何年かかると思いますか。
まずは獣医師免許をとるための獣医系大学で6年間勉強します。
さらに、最近では、獣医学共用試験という制度が始まっています。
獣医学共用試験とは、4年生になった時に受験する試験で、この試験に合格しなければそのあとの臨床学習に進むことができない。といった大変厳しい試験です。
この獣医学共用試験の内容は、知識を評価する試験と、診察の技能と態度を評価する試験の2種類で構成されています。
この試験は動物の先生になる人は必ず受けなくてはいけません。
さらに、6年になった時にも所定の卒業論文も提出しなければいけません。
この時、卒業論文を書くために所属するのがいわゆる「研究室」です。
研究室への配属は3・4年生の時に決まってくるので、研究室ごとの特徴をしっかり把握しておくと自分が進むべき道が見えてきます。
重大な選択をするときですね。
その後、晴れて獣医大学を卒業したら、国家試験が待っています。難易度の高い国家試験に合格して、獣医師免許をとることができます。国家試験は年1回ですので、不合格の場合は働きながら翌年の国家試験に備えることになります。
国家試験に無事合格し、獣医になってもすぐには動物病院を開業することはできません。
獣医師免許をとった後は、2~3年程度研修医として働きながら勉強を重ねます。
その後やっと一人前の獣医として開業できるのです。
獣医になるために最低6年、その後少なくとも2~3年は勉強を重ね、ようやく獣医師として動物病院を開業するまでの準備ができてきます。
ただし、動物病院として開業するには、開業エリアの選定や診療方針の決定、「ホームドクター」か「専門医」なのか、あるいは「トリミングやペットホテルを併設するのか」といった診療内容を考えていくことが必要です。
さらに、開業のための資金も必要になりますので、しっかりと計画を立ててから行動することをお勧めします。
獣医になるための学校と試験
獣医になるためにはどんな難関が待っているのでしょうか。獣医を目指すには、まず獣医学部に入学しなければいけません。しかし、獣医学部に入るのは非常に狭き門となっています。
その倍率は、単純計算で24倍といわれています。
私立で人気がある早稲田大学も各学部において約4~6倍です。
比較すると、獣医学部がいかに狭き門かということがわかります。
獣医学部を設置している大学は全国で国公立が11校で入学定員が約370名です。
私立に至っては、6校で入学定員は約590名とされ、双方合わせても1,000名にも満たないのが現状です。
その枠の中でも、人気がある日本大学や日本獣医生命科学大学の場合、競争率は10倍以上にもなるといわれています。
そのため、浪人する可能性も高く、現役生と浪人生の合格者の割合は、現役生は、約34%、浪人生は約60%と、ほぼ倍近い人が浪人生として獣医学部に入学していることがわかります。
しかも現役生の中には、推薦入試も含まれていますので、一般入試の合格者はほとんど浪人生というのが実状です。
また、浪人生の勉強の場は、獣医学部受験を専門とした塾が多数を占めています。

では、獣医学部への入試問題はどのようなものなのでしょうか。
細かくは、各大学によって違いがありますので、各大学の情報を確認してください。
例えば、国立の獣医学部では数Ⅲが必須の大学と必須ではない大学があります。
理科も必須の大学とそうではない大学もあります。
また、国立大学の獣医学部の場合は、センター試験の点数配分の割合が高いので、入試対策としては、センター試験で88%以上の点数をとることを」合格最低ラインとして目指すことになります。
その上、2次試験の初級問題は確実に解けるような対策が必要です。
私立大学の場合、入試問題を作成する担当者が少ないためか、過去の問題からの大きな変化傾向はみられません。ですから、6~10年分の過去問題やそれ以前の問題を覚えておくと有利です。特に数学と理科はこの傾向が強いです。
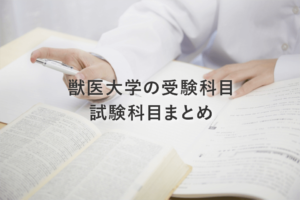
参照)獣医大学一覧
獣医になるための試験
獣医になるために必要な獣医師国家試験について紹介します。難易度が高い試験ではありますが、受験者の約77%が合格しています。合格者の内訳は、新卒の合格率は約90%と高く、既卒の場合は約30~50%と合格率が下がっています。
獣医学部の大学を卒業してすぐに、資格試験を受けたほうが有利な傾向にあるのは間違いなさそうです。
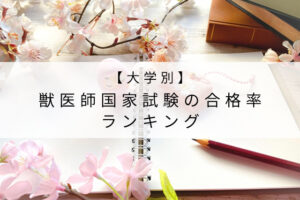
獣医師国家試験についてはこちらの記事をご覧ください。
獣医になるためにかかる費用
ここまで、獣医になるためについて説明してきましたが、実際にかかる費用はいくらになるのでしょうか。
私立大学は各大学によって違いはありますが、国立大学の場合は文部科学省によって標準額が
決まっていますので、一律の金額となっています。
主な国立大学の場合
入学料:282,000円/授業料:535,800円
初年度学費:817,800円/2年時以降学費:535,800円/6年間学費:3,496,800円
また、公立の大阪府立大学の場合、居住地によって学費に違いがあり居住地が大阪府内の場合、学費が安くなります。
私立の場合はもっと高くなってきます。
入学料や授業料については、こちらをご参照ください。正確な情報は、それぞれの大学ホームページを参考にしてください。

獣医の給料と年収
獣医の平均年収は、一般に人々がイメージする金額より安いかもしれません。
厚生労働省によると、獣医師の 平均年収は約685.7万円 です(参考:厚生労働省)。
勤務する施設や雇用形態によって収入には大きな差があります。
例えば、日本中央競馬会(JRA)の獣医師の平均年収は約650万~1,200万円と高水準であり、 独立開業した場合の年収は500万~1,000万円とされています。一方、勤務医の場合、年収は約250万〜400万円とやや低めの傾向があります。
もちろん、地域によっても違いがありますが、動物病院に就職した場合、大体月23万円からスタートでしょうか。開業獣医師では500万~2000万円以上(成功すれば高収入)となります。
地方公務員の獣医として就職した場合は、他の地方公務員のお給料と同等になります。
こちらも地域によって給与形態が違ってきますが、一部では民間企業(動物病院)よりも安い場合があります。
医薬品や製薬関連の企業に就職した場合は、企業の規模や、業績によって大きく違いがあるため、実際の企業の募集要項をよく確認することが大切です。
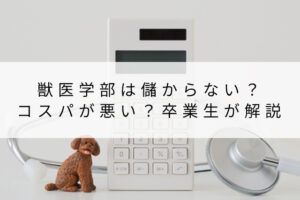
また、獣医として独立するには、平均的には30代後半くらいといわれています。
独立までにかかる理由としては、
・技術の粋銃や経営スキルを向上するための勉強期間
・設備投資等の必要な資金がたまるまでの期間
・条件のよい土地を見つけるまでの期間
といった点が上がられます。個人で開業する際に必要な最初の資金としては、最初の土地代や設備費と、運転資金込みで約3,000万円かかるといわれています。
そのため、日本政策金融公庫などに融資を申し込んで開業するケースが多いです。
獣医になるためには、時間とお金が必要です。
そして、獣医になるためには、「動物が好き」だけでは務まりません。
飼い主さんとのコミュニケーションをしっかり取れるコミュニケーションも大切です。
しかも、チームで医療を行うのであれば、なおさらです。
就職先によって、お給料にも差がありますので、獣医になった先に何を目指したいのか、今から考えてみるとよいかもしれません。
自分が、動物病院として独立したいのか。その場合、ペットと人を相手にする動物病院に勤務しながら資金をためて独立開業を目指すのか、大型の産業動物を専門とした動物病院に勤務して独立開業を目指すのか。それぞれの道で働き方、考え方、準備の仕方が変わってきます。
独立開業する際は、経営に関する勉強も必要となってきます。しっかりとした事業計画と、資金計画、このような勉強も必要になってきます。
動物病院以外に就職した場合でも「動物がかわいいから」だけでは仕事は続けられません。
獣医として動物の死と正面から向かい合うことができなければ務まらない仕事です。
これから獣医として働きながらぜひ、命の大切さ、飼い主の責任を大勢の人に広めるようにしてほしいと思います。
保健所で処分される命が少しでも減るように、無責任な飼い主を増やさない啓蒙活動や、TNR活動などの地域課題解決に率先して取り組むことができる獣医になってください。
獣医になるにはどんな高校を選べばいい?
獣医になるには高校選びも重要となってきます。
結論から言うと、なるべく偏差値が高い学校であれば、どこであっても問題ありません。その中でも理系の学科などを選ぶとなお良いでしょう。
というのも、獣医学部のある大学は、比較的偏差値の高い学校が多く、また、医療を学ぶため、覚えることも多くあります。
必然的に勉強量も増えるので、高校のうちから基礎的な勉強ができるよう、準備しておくとよいでしょう。


