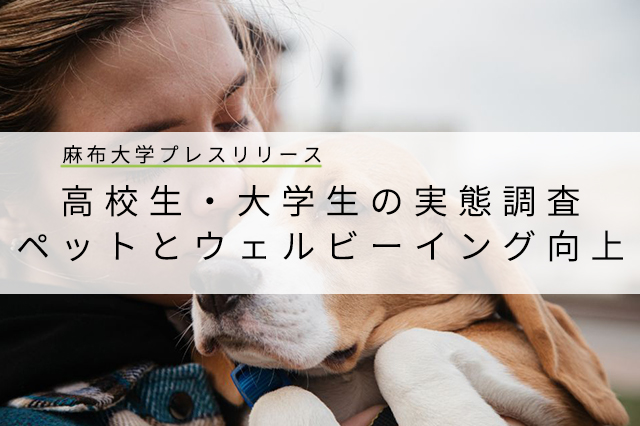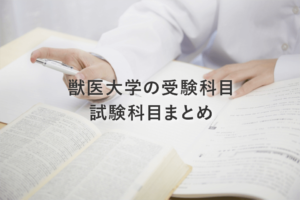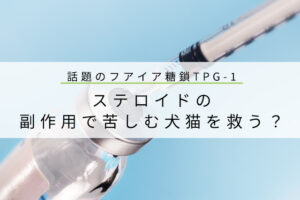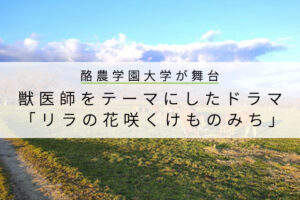麻布大学獣医学部の研究チームが、高校生・大学生を対象に、ペットとの関わりとウェルビーイング(心身の健康や幸福感)に関する実態調査を実施しました。
この調査は、若者の精神的健康や社会的つながりにおけるペットの役割を明らかにすることを目的としています。
その結果、社会的な孤立感を抱える若者が、ペットとの交流を通じて高いウェルビーイングを維持していることが示されました。この研究は、獣医大学を目指す受験生や獣医大学生にとって、動物と人間の関係性を深く理解する上で重要な示唆を提供しています。
麻布大学が高校生・大学生の実態調査 ペットとウェルビーイング向上

麻布大学(学長:村上賢、本部:神奈川県相模原市)獣医学部介在動物学研究室の子安ひかり特任助教、永澤美保教授、菊水健史教授、京都大学医学研究科の村井俊哉教授、東京都医学総合研究所の西田淳志センター長らの研究チームは、高校生・大学生を対象に、イヌやネコとの関わり方、社会的疎外感(文化的離反尺度)、およびウェルビーイングについてのアンケートデータを解析したというプレスリリースが発表されました。
調査結果
調査の結果、社会的な孤立感を抱える若者が、ペットとの交流を通じて高いウェルビーイングを維持していることが示されました。
特に、イヌやネコに対して心の内を打ち明けることで、感情的な支えを得ている傾向が明らかになりました。
これは、ペットが単なる癒しの存在を超えて、若者の精神的な健康を支える重要な役割を果たしていることを示しています。
調査対象と目的
この調査は、高校生・大学生を対象に、ペットとの関わり方や社会的疎外感、ウェルビーイングに関する実態を明らかにすることを目的として実施されました。
若者の精神的健康や社会的つながりにおけるペットの役割を理解することで、今後の教育や支援策に役立てることが期待されています。
調査背景
近年、若者の間で社会的孤立や精神的なストレスが増加しており、ウェルビーイングの向上が重要な課題となっています。その中で、ペットとの関わりが精神的な支えとなる可能性が注目されています。
本調査は、こうした背景を踏まえ、ペットが若者のウェルビーイングに与える影響を科学的に検証することを目的としています。
麻布大学獣医学部について

麻布大学獣医学部獣医学科は、獣医師を目指す人にとって学びの幅がとても広く、実践的な経験も積める魅力的な学部です。もともとは1890年に東京獣医講習所としてスタートし、長い歴史のなかで多くの獣医師を育ててきました。現在は「人と動物がともに生きる社会」の実現をめざし、「獣医」「動物」「健康」「食物」「環境」という5つの視点から幅広い学びが展開されています。
特に獣医学科では、動物の病気のことだけでなく、動物福祉や感染症対策、公衆衛生、さらには地球環境とのかかわりまで、幅広く学べるカリキュラムが特徴です。将来は動物病院だけでなく、研究機関や行政、食品関連など、さまざまな分野で活躍する道が開かれています。
今回の調査を行ったのは、獣医学部にある「介在動物学研究室」。
この研究室では、イヌやネコなどの動物が人の心に与える影響を科学的に研究していて、動物と人の心のつながりを大切にする視点から、多くの研究が行われています。動物との関係を通じて人の健康や幸せ(ウェルビーイング)を考えるこの分野は、獣医師をめざす人にとってもとても興味深いテーマです。

獣医学と聞くと動物医療に関する学問だと思いがちです。それは間違っていませんが、今回の調査のように、動物と人間の関係性や人のウェルビーイングといった、研究対象がヒトであることも珍しくありません。
獣医大学卒業生の私も、入学後教授に「獣医学は動物のための学問ではなくあくまでもヒトのための学問である」と教わりました。 この調査のニュースはそれがわかるようなニュースだったのではないでしょうか。
獣医大学を目指す受験生や獣医大学生にとって、動物と人間の関係性を深く理解することは、将来の職業においても重要な視点となります。
Pettie獣医大学ではこのようなニュースも取り上げていきたいと思いますので今後もぜひチェックしていってください。